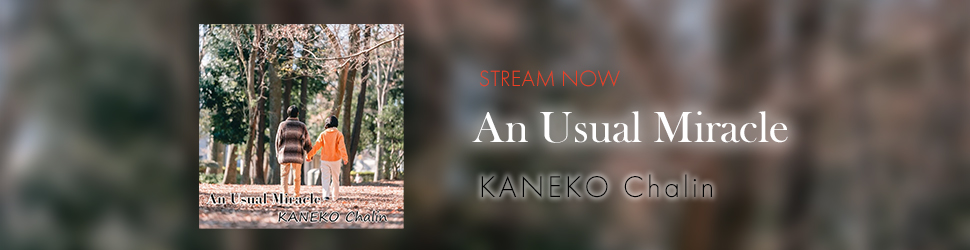Thelonious Monkの前にも後にもThelonious Monkの音は鳴らない。彼の音楽はJazzだとかBe-bopだとかではなくThelonious Monkだ。
たいていの巨人はたくさんのフォロワーを生み出す。だが、どことも陸続きでない、離れ小島のような巨人もいる。その音楽はものすごく多くの人を、そして、ミュージシャンを虜にするのに、それに続く人がいない。というか、続く方法がわからない、もしくは、続けることに意味が見いだせない、そんな感じなのだろうか。
Thelonious Monkはまさにそんな巨人の一人だと思う。一つ一つの音は粒だっているけど、それが空間のどこに配置されていくのか、全く予想がつかない。僕のMonkとの出会いだった「Monk in Italy」の1曲目のこの曲を。
Apple Muisc
Amazon
なんで急にThelonious Monkなのかというと、先日「Monk in Europe」という映画を見たからだ。映画の中のライブのリハーサルで、実力派ぞろいのホーンの演奏者たちが曲の構造がわからず戸惑っているのをCharlie Rouseが一生懸命教えているのをMonkはピアノの椅子に座って無表情に見ているがものすごくMonkぽっくて面白かった。
さて、続いてもJazzから。こちらはミステリアスというより、「素」過ぎて誰にも真似できない巨人を。彼の音楽には何のけれんみもない。舞台の上で演奏されているのではなく、車の助手席で歌っているように歌い、川辺でくつろいでるときに遠くから聞こえてくる練習のような感じでトランペットを吹く。僕にはそんな風に聞こえる。でも誰も彼のようには吹けないし、歌えない。人生は無茶苦茶だったけど、音楽は本当に普通でクールなChet Bakerの曲を。
「Yardbird Suite」Stan Getz& Chet Baker Quartet本家のCharlie ParkerとDizzy Gillespieの演奏と聞き比べてみると、その違いがよくわかって面白い。
もう一人、とてつもなくナチュラルで誰にも真似できないこの人の歌を。
「Oração Ao Tempo」マリア・ベターニアBillie Holidayは個性的なだから「モノマネ」しやすいけど、Ella Jane Fitzgeraldは普通で自然体だから「モノマネ」しづらいと聞いたことがある。Mariaもそんな歌い手だと思う。本当に簡単そうに普通に歌う。だからこそ気持ちいいんだけど。
次は偉大なこのバンド、The Bandの曲を。「いやいや、アメリカーナとかサザンロックとかフォロワーたくさんいるのでは?」と突っ込んでいる人もいるかもしれないが、僕が話したいのはGarth Hudsonだ。彼がロックバンドにいるのは奇跡だ。The Bandは十分に優れたロックンロールバンドだけど、Garth Hudsonがオルガンを弾くからこそ特別なロックロールバンドに変身する。Garthのオルガンは曲の前面に出てくることはあまりないけど、ミキサーの底で回っている歯のように、曲の底の方から曲をグルングルンかきまわして、シンプルな曲を混乱へと昇華させる。Butterfieldのトレインとしか言いようのないハーモニカもいいし、Levon Helmのボーカルも素晴らしいけれど、暴れまわるGarthがききもののこの曲を。
「Mystery Train」The Band with Paul Butterfieldもう1曲、フォロワーがいないというようより、自分自身の音楽がつながっていないように感じるこの人の曲を。ジギー・スターダストからソウルへそしてベルリンからロックアイコンへ。わざととか、額に汗して変化するのでなく、まるで昆虫の変態のように変化していく。純粋に変化しているだけで別に向上しているわけでもない。まさに”Change”だ。
「Changes」デヴィッド・ボウイさて、最後にいつもの通り僕の曲を。僕は別に巨人でもないし、もちろん、フォロワーもいないので、今回書いた内容に合う曲というのも難しいのだが、昨年末にかいた曲を紹介します。いつもの通りフォーク調の曲だったのだが、BandLabにあげたら、何人かがどんどん音を足してくれて、最終的にちょっとミステリアスな曲になったのでこの曲を。しかし、この重めの歌詞にDoo-wop調のバックコーラスは想定外だったなあ。

365 days will have passed in tomorrow 作詞作曲:金子茶琳
365 days will have passed in tomorrow
Sometimes fast, sometimes slow
Like a river from the mountain to the sea, each day just flow
Sometimes fun, sometimes sorrow
A lot of drama was written and many times I enjoyed
Sometimes laughed, sometimes cried
I drank a lot of beer to take home, at last got to drink freshly poured
Sometimes happy, sometimes bitter
New babies were born, and some passed away
New love started and lost on the way
New songs were born, and the old still stay
There are not enough love songs to play
I just wanna be with you in New Year's Day
A lot of hard rain had come again and again and again
Some lives passed, left lives in pain
My old daddy was in hospital, but I could never see
Some lives saved, someday we'll meet
That day all watched TV that The Capitol was attacked and burned
Some crimes punished, some crime put under
A celebration of peace will be hosted in the land of genocide
Too many killers, too many lies,
New babies were born, and some passed away
New love started and lost on the way
New songs were born, and the old still stay
There are not enough love songs to play
I just will be with you in New Year's Day
365 days will have passed in tomorrow
Sometimes fast, sometimes slow
Like a river from the mountain to the sea, each day just flow
Sometimes fun, sometimes sorrow
こちらもオススメ
音楽好きのつぶやきVol.1 Island In The Sun - ウィーザー
EmAmDG、シンプルなコードのシンプルな繰り返し。このコードで今までたくさんの曲がかかれてきたのは胸がしめつけられるような郷愁を誰もが覚えるからか。音楽は不思議だ。純粋に音だけで心が動く。このコードで書かれた曲の中で僕が最初に思いつくのはこの曲。Weezerには胸がしめつけられるような曲が多いけどこの曲は極めつけ。ギターのイントロだけで景色から色が失われていく気がする。 Apple Music Amazonhttps://amzn.to/2YDtWKg 最後に紹介する僕の曲のサビの部分で“Swingin ...
音楽好きのつぶやきVol.16 MADAN - サリフ・ケイタ
今回は声に注目して曲を選曲したいと思う。ジャズも大好きなので声が入ってない音楽もよく聞くけれど、やっぱり「歌」が大好きだ。ジャズの中でも一番好きなのはトランペットなんだけど、それはやっぱり一番、人の声に近いからかなあと思う。声に注目してと言いながら、最初はまるで歌っているようなClifford Brownのトランペットから。 さて次からは人間の本当の声に注目します。この人のどこまで高く突き抜けていく声はやっぱり格別だ。歌を聞いていると、まるで彼の声の翼に乗って空高く舞い上がる。病気になってかつての輝き ...
音楽好きのつぶやきVol.11 Sunny Afternoon - キンクス
オルタナティブということではないんだけど、その時代のメインの音とパラレルにちょっとずれている音楽のほうが時代のど真ん中の音楽より好きだったりする。多分、僕が天邪鬼だからだ。今回は3大〇〇から漏れちゃってるけど、「俺的には1番」という音楽を紹介したい。 3大UKロックバンド(The Beatles, The Rolling Stones, The Who) ビートルズマニアやストーンズファン、フーの信望者には結構出会うが、キンクスフリークに会うことは滅多にない。でも、僕はThe Kinksが大好きだ。 ...
音楽好きのつぶやきVol.4 Everything about it is a love song - ポール・サイモン
私が好きな生きているミュージシャンは殆ど60歳以上だ。(殆どはこの世にいない。)若くにして亡くなったミュージシャンは若いままでかっこいいが、年を取ったミュージシャンはほぼみんなダンディになる。数年前、Bob Dylanのライブハウスツアーのコンサートに行った。ギターは一度も弾かず、マイクを持って、時々あまりうまいとは言えないキーボードを弾きながら歌っていたのにもびっくりしたが、もっとびっくりしたのは、新作だった「Tempest」からの曲がメインで、いわゆるよく知られた曲は殆どやらなかったこと。「俺の新作を ...
音楽好きのつぶやきVol.22 Piano Man - ビリー・ジョエル
ビリー・ジョエルの1990年のニューヨーク・ヤンキー・スタジアムでのライブ映像(LIVE AT YANKEE STADIUM)を映画館で見た。最高。録音音源もいいけど、ライブがいい。ビリーは根っからのエンターテイナーだ。とにかく、来てくれた人を愉しませたい。バンド全体がそんな感じ。もちろん、曲がいい。ヒット曲のオンパレードなので悪いわけがない。もう何十度目かのビリーのマイ・ブームがやってきたので、今回はビリーの曲を紹介したいと思う。まずは、僕が中学生の頃、兄貴の部屋から借りてきたこのアルバムから。 こ ...
音楽好きのつぶやきVol.21 Sitting In My Hotel - ザ・キンクス
ザ・キンクスがRCA時代の名盤である『マスウェル・ヒルビリーズ』と『この世はすべてショー・ビジネス』の発売50周年を記念してリマスターやら未発表リミックス等いれこんだCDを発売したというニュースを聞いて、改めて、2枚を聞きなおしてみた。(結構、この2枚はよく聞くので、改めてっいうほどではないのだが)私はちょっとしたキンキーフリークなので、初期のとんがったキンクスもちょっとずつメインからずれていく頃のキンクスも後期のいなたいロックンロールをやってるキンクスも全部好きなのですが、やはり、この2枚は別格ですね ...